

JAEN
Company Brochure PDF


激変する映像業界の中で、TYO Chief Producerの面川正雄は、地域密着のプロジェクトからグローバル企業の案件まで幅広い映像を手がけてきた。独自のスタイルで多くの人の心を動かし、受賞作品も多数。戦略以上に「チームづくり」を大切にし、相手の思いを汲み取ることや、現場の雰囲気を重視する。テレビCM全盛時代を経て、生成AI時代が到来する中、さまざまなチャレンジに取り組みながら、TYOの強みである「心を動かす、伝わる物作り」を体現し続けてきた。面川にプロデューサーとしての哲学を聞いた。
──自治体から大手企業、グローバルブランドまで、幅広いクライアントと仕事をされていますね。
毎回一期一会ではなく、仕事を通じて新たな仲間ができて、初めてお仕事する方々との新たな関係が生まれます。そこからまた仲間ができて、また違う仕事に発展していきます。
仕事は極力選ばず、SNSやWebサイト制作といった、CM映像以外のプロジェクトや、規模が小さい案件でもできるだけ相談に応じるようにして、自分自身も勉強しながら手がけられる仕事の幅を広げられるようにしています。この柔軟性が私の強みの一つになっているのかもしれません。
損得勘定ではなく「楽しそうだな」という直感的な興味から新しいことに挑戦する姿勢や、純粋な「応援」の気持ちや熱量がクリエイティブににじみ出て、それが多様な経験と人脈の拡大につながっていると思います。
規模の大小や予算の多少に関わらず、その案件にどこまで心血を注げるかが大事だと思っています。結果的にクライアントとの信頼関係を深めることができているのかもしれません。厳しい視点を持ちながらも、真剣に取り組む姿勢を評価してくれるクライアントとの信頼関係の中で、本当に意味のある仕事ができていると感じています。
最近は直接私のところにお声掛けをいただくケースも増えていますね。現在制作に取り組んでいるグローバルブランドのクライアントの方からは「面川さんと仕事ができてよかったです。またお願いします」と、継続して仕事をご依頼いただいています。

──映像制作で大切にしている考え方を教えてください。
正直申し上げますと、それほど戦略的に考えているわけではありません。「涙が出るほど感動させたい」といった、ざっくりとしたイメージで制作を始めることが多いです。
私は競争よりも協調を重視するプロデューサーだと思います。勝った負けたよりも、プロセスや内容が大事です。根幹には、チームでよい作品を作りたいという思いがあります。対クライアントにとどまらず、あらゆるコミュニケーションを大切に考えています。
「仕事は仲間をつくってくれる」と考えていて、現場の雰囲気づくり、チームづくりにはこだわっています。険悪な制作現場は本当に苦手で、みんなが楽しく仕事できて、結果、良いものができる環境を作るよう心がけています。
打ち合わせや現場では「この人はイエスと言っているけれど、内心は違うだろう」とか、「なんとなく気分を害しているのではないか」といったことを察知して、言葉にしていないけれど、こう言いたいのだろうということを推測し、配慮しています。
メールやテキストコミュニケーションでは伝わらないことがよくあります。実際にちゃんと会話をし、丁寧に提案すること。そこは留意していますね。

──制作において大切にしている感情はありますか。
私の仕事への取り組みは、純粋な「応援」の気持ちから生まれています。自分が心を動かされて、応援しているから、その熱量がクリエイティブに出ていると思います。一緒にやっている仲間たちとも、そういう部分で共感できることが多いです。
まず徹底的に好きになることが大事だという信念のもと、一つ一つの案件に全力で取り組んでいます。本当に応援しているから、クライアントには徹底的にヒアリングを重ねて、企画のすり合わせも丁寧に行います。
出来上がった映像をクライアントや関係者の方々に見ていただいて感謝の言葉をいただいたり、時に涙を流されている姿を見るのは、作り手として嬉しいことです。クライアントやプロジェクトに対する熱量や愛が原動力となり、作品の質にも直結しているのだと思います。
──広告業界の変化をどのように感じていますか。
これほどスマートフォンで映像を視聴する時代になるとは思いませんでした。テレビCM自体はどんどん厳しくなっていくのではないかと言われていますが、テレビ CMの制作を通じて培った知見やノウハウは、様々なフォーマットにおいて、企業や社会に必要とされているという感覚があります。
CMを制作するだけでなく、SNSでも配信したり、フォーマットに合わせて横型だけでなく縦型動画でも配信したりなど、複数パターンで映像を制作するケースが増えています。
最近個人的に挑戦しようとしているのが縦型画面に合わせたドラマです。TikTokなどで縦型のショート動画が流行っているので、継続的なコンテンツの企画制作に取り組んでみようと、企画を立てています。
また、これまでテレビCMなどで映像が求められていた役割以上に、より上流と言える企業課題全般に映像が必要とされているという感覚があります。
TYOの「ステートメントムービー」のように、プロモーションではなくコミュニケーションとして、映像に本気で取り組まなければいけないと感じている経営者やリーダーが出てきて、経営や組織運営においてもより上質な映像が求められているように感じています。
ステートメントムービーのような映像制作でも、結局変わらない本質としては、徹底的にクライアントのことを好きになってのめり込んでいくということが大事なんだと思います。
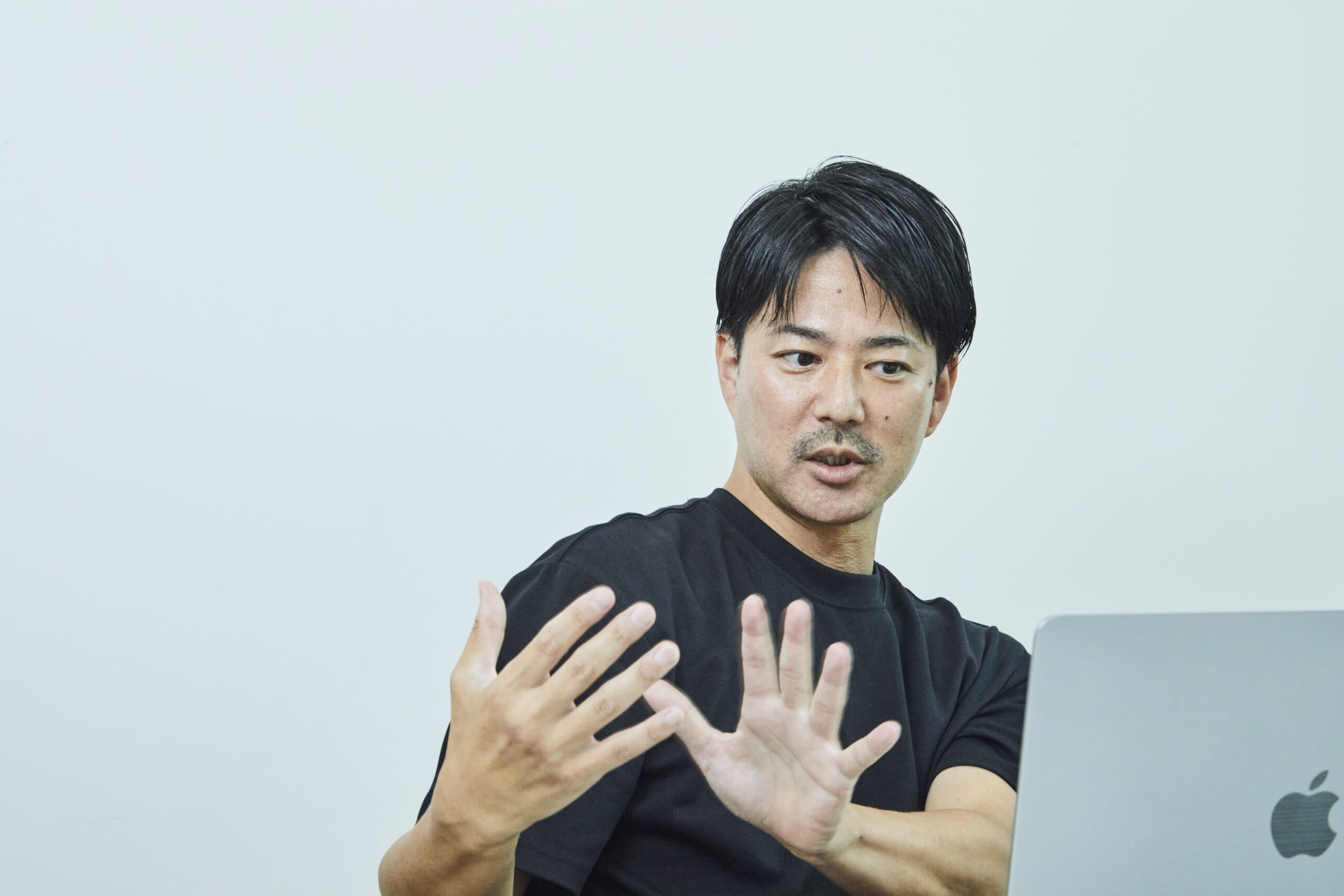
──TYOの強みについてはどう捉えていますか。
MONSTERは長い歴史があり、ずっと映像制作の第一線で活動し続けてきた実績があります。私自身も先輩方の背中をずっと見てきて、その仕事ぶりを間近で体得することができたのは大きな財産です。
映像業界はネットやスマートフォン、縦型動画の普及で、どんどん新しいプレイヤーが参入してきています。そんな中で、TYOの歴史に裏付けられた総合力はやはりすごいものがあると思います。これだけの体制を持った映像の会社はなかなかありません。
人の心、エモーションをしっかり捉えることができるかということが、TYOにおける映像制作の仕事の大前提にあることだと思います。「伝わるかどうか」という点に対して、当たり前のようにかけている力の入れ具合やコミットメント具合が、やはり違うと思います。
TYOのクリエイターたちは、良い作品を制作するために心と体、両方のエネルギーを注いでいます。その基準がとても高いと思うんですよね。
限られた時間や予算の中で、それなりのものを作るか、せっかく作るなら圧倒的なものを作るか。一つひとつの「当たり前」の基準が高い。TYOのメンバーたちの中にはそれに気づいていない人も結構いると思いますが。心を動かす、伝わる物作りをするという、TYOのミッション・ビジョンがやはり無意識のうちに全社に浸透しているのだと思います。新しい事業も立ち上がってきていますし、みんな結局、映像が好きなんですよね。
──生成AIについてはどう捉えていますか。
生成AIの進化はものすごいと思いますし、実際に制作の現場で使われることも多くなりました。テレビCMやプロモーションの映像は今後もっともっと作れるようになっていくと思います。
一方で、人間の仕事の変わらない価値もあると思っていて、ドキュメンタリーは絶対にAIでは作れない。ドキュメンタリーは人と人の関係性やストーリーがそのまま表れるものです。ファクトをベースにした真実に迫るインタビューも無理でしょうし、細かいニュアンスや温度感を表現することなどもAIにはしばらくは無理だと思っています。
そういう意味では、生成AIが映像制作を担うようになっても、人間にしかできない仕事としてドキュメンタリーは生き残るのではないでしょうか。
今年、あるクライアント企業のドキュメンタリー制作の仕事で中国にロケに行きました。現地の人たちの表情、動き、その場の空気感は、実際に現地に行かないと撮影・表現できません。そういう意味で、ドキュメンタリー映像は今後も価値を持ち続けると思います。個人的には、AI時代も変わらず、見る人の心に残り、思わず何度も見返したくなるような映像を作り続けることが目標です。最終的には、自分自身が深く心を動かされるものを作りたいですね。

面川プロデューサーが語る、受賞作・話題作の裏側。前編はこちら